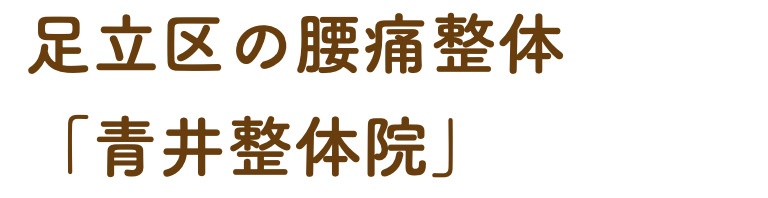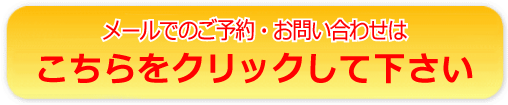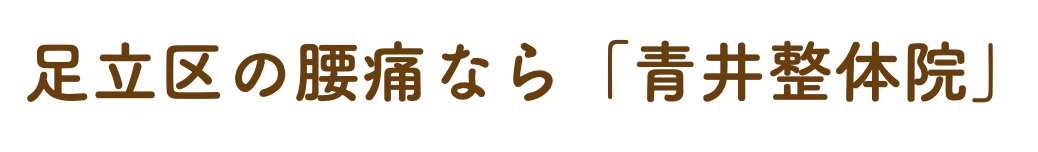綾瀬 足低筋膜炎の可能性
2017-07-15 [記事URL]
足の裏に痛みが起こった場合には足低筋膜炎の可能性もある
立ち仕事が多い人やスポーツをしている方に関しては、足の痛みはどうしても避けられないものです。
長時間の歩行や立ち仕事によってかかとの内側に痛みが起こったり、階段を昇る時やつま先立ちした時などで痛みが強くなったりするのなら足底筋膜炎になっている可能性が考えられます。
また、陸上競技やバスケットボールなどランニングやジャンプの多いスポーツをすることで、足の裏に痛みを感じる時も発症が疑われます。
その他にも、中年女性に多いといわれる朝起きた一歩目に痛みを感じけど、動き始めると徐々に軽くなるなどの症状が起こるのも発症している可能性が高いと考えられます。
では、そもそも足底筋膜というのは何なのでしょうか?
人間の足は指・土踏まず・かかとなどで構成されていて、外見からは分からないですが足は骨同士が靭帯でつながっていて、筋肉・腱・足底筋膜で補強されています。
この中の足底筋膜は、足の指の付け根からかかとにかけて足の裏に膜をはっている構造をしていて、足が地面に着地した時などに衝撃を受け止める働きをしているのです。
このように立ち仕事やスポーツなどが原因で起こる足の裏に痛みを感じる足底筋膜炎を、どのようにして治すでしょうか?
その前に診断する方法ですが、まず基本的に受診するのは整形外科で、病院で痛みの有無・痛みのある場所・足の変形などを検査します。
その結果、足底筋膜とかかとの骨の付着している部分にあたる土踏まずとかかとの境目を押されると痛みを感じると言った症状があると発症していると判断されます。
また、長時間立ったままや歩く・走る・歩き始めの時に足底筋膜とかかとの骨の付着部周囲に痛みを感じる場合も、同様に発症とは判断されます。
それから、神経の圧迫や障害、筋・腱の部分断裂などの疾患が否定される場合にも、発症していると判断されるのです。
病院での実際の治療としては、保存療法と手術療法の2つに大きく分けられ、基本的に保存療法から実施されて、それでも改善が見られない場合には手術療法が検討されるのです。
まずセルフケアとして、足に負担をかけないよう運動を制限しますし、足に合う靴に変えるなどの工夫が行われます。
それに加えて病院では、理学療法のアキレス腱や足底筋膜のストレッチによる治療が実施されます。
ストレッチの一例としては、足の裏が伸びるように足のつまさきから足首にかけて反らします。
これを10回1セットとして1日3セット以上を目標に実施しますが、あくまでも方法は医師と相談しながら決めることが大切です。
また、足底板を利用して自分の足の形に靴が合うように調整することも実施するケースもあります。
基本的に直接治してくれる薬は現段階ではありませんが、痛みに対しては痛み止めの飲み薬を、また湿布などの外用薬を使用すると言った薬物療法も行うことがあります。
また、非常に強い痛みが起こっている時には、強い炎症を抑える作用のある薬を注射することもあるのです。
こうした保存療法でも改善しない重症の場合には、足底筋膜の付着部を切り取る手術やかかとの骨化した部分を切除すると言った手術が行われます。
綾瀬 足低筋膜炎の可能性なら、田中カイロプラクティックセンター綾瀬整体院にお任せください。